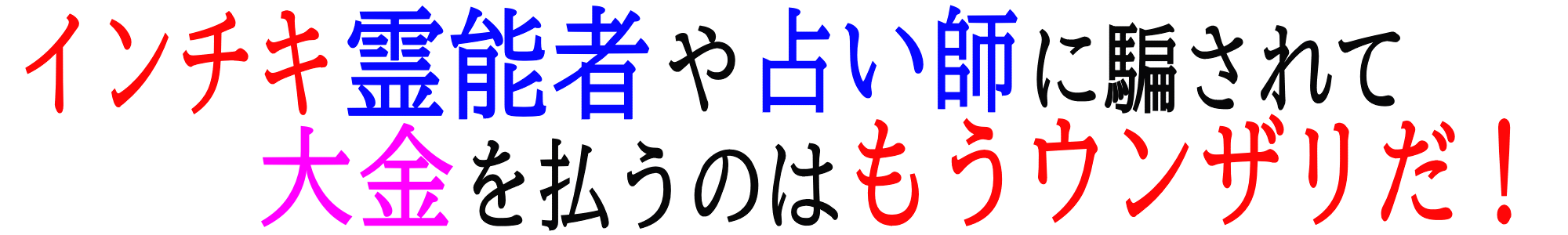



陰陽師の歴史
6世紀に誕生した大和朝廷は、国家運営に必要な思想・技術体系とその専門家を、中国や百済から積極的に導入した。514年の継体天皇の時代には百済より五経博士が来日し、欽明朝(539年~571年)の時代には、易博士、暦博士が来朝する。推古朝の602年には、百済の僧、観勒(かんろく)が、暦本、天文地理書、遁甲(とんこう)方術書を献じたとする。
さらに西暦660年、百済は国家滅亡となり、「陰陽の思想」の専門家たちが多数、百済や高句麗から大和朝廷へと亡命を果たす。彼らがもたらせた思想と技術は、陰陽五行説、儒教、道教、密教仏教の習合的思想であり、そこから派生した易風水学・天文暦学・病理学・呪術妖術学などであった。そして多くが官位を授けられ、大和朝廷の組織に組み込まれていくことになる。
誕生して間もない大和朝廷が、大陸ですでに実績を発揮したこの「思想と技術の総合的な体系」を率先して学ぼうとしたのは至極当然のことだっただろう。
特に天武天皇(在位:673年3月20日~686年10月1日)は高い関心を示し、すぐに術数(天文や暦数を元に未来の吉凶を卜う技術)の知識を「壬申の乱」でも活用したようだ。また、675年に天武天皇は官人のための病院である「典薬寮(てんやくりょう・くすりのつかさ)」(当時はまだ「外薬寮」と呼ばれていた)を設置する。ここには呪文や呪符を用いて病人の邪気を払う「呪禁(じゅごん)師」が配置されている。さらに718年、天武天皇は陰陽師の活動基盤であり育成機関となる「陰陽寮」を設立するのである。
飛鳥時代の陰陽師
日本における「宮廷陰陽師」の登場は、718年(養老2年)である。この年「養老律令」において、中務省の内局小寮として「陰陽寮」が設置される。
陰陽寮とは、律令制における中務省機関のひとつで、占い・天文・時・暦の編纂、後に呪術等を担当する部署である。その基幹となった学術・技術・思想体系は、百済経由で中国から伝来された「陰陽の思想」(儒教、仏教、密教、道教など各宗教思想体系)とそれに基づいて派生した占術・呪術の知識・技術である。ちなみにこの「陰陽の思想体系」は、平安時代になると「陰陽道」と呼ばれるようになるが、飛鳥時代にはまだ「陰陽道」という言葉は使われていない。
陰陽寮には、上は総指揮官である長官(陰陽頭)から、陰陽師を養成する陰陽博士他、さまざまな役職が存在しているが、飛鳥時代の陰陽師は主に、「吉凶占い、方位占い」を行う」技官だった。現代で言うなら風水師に近いものと考えていいだろう。例えば遷都の際などは、陰陽師が朝廷に対してさまざまなアドバイスを行うわけである。
陰陽寮初期の陰陽師は、大陸から亡命した専門知識人で構成され、陰陽師職に就きながら、日本人の陰陽師育成を急ピッチで行っていたようである。当時の官人たちの出勤状況を記す資料によれば、当時の陰陽師たちの平均出勤日数は「年300日出勤」である。他の官人たちが「年240日出勤」なので、いかにハードワークを強いられたことがわかる。
陰陽師というと呪術と連想されがちだが、当時、呪術色が強かったのは陰陽寮よりむしろ「典薬寮」である。典薬寮の「呪禁(じゅごん)」という部署では、呪文や呪符を用いて病人の邪気を払う治療が盛んに行われていた。
その後、陰陽師たちにも呪文や呪符の知恵は授けられ、飛鳥時代末期頃には、陰陽師が国や土地の邪気払いを担当し、呪禁師は病人の邪気を払うという役割分担になったようだ。しかし飛鳥時代においては、あくまで陰陽師のメイン業務は「占い師」、「風水師」である。また、飛鳥時代の貴族たちの間では現代で言う「夢分析」も流行っていたため、貴族たちが見た夢の吉凶占いも大切な仕事だったようである。
陰陽道の教えは門外不出の機密事項であり、一般庶民が学ぶことは許されなかった。また、飛鳥時代においては陰陽師といえば「官人」であり、その能力の恩恵を受けるのはあくまでも天皇や貴族、官人である。一般市民は陰陽道を学ぶことも、陰陽師の能力に触れることも許されなかった。
こうした陰陽寮を現代の官庁のイメージで言うと、「内閣府」の最重要な一部であり、「文部科学省」機能に加え、軍事戦略的な判断も行う「防衛庁」、国家機密を管理する「公安警察」の役割をも兼務したものだった。このように飛鳥時代において「陰陽道」は、国家を支える思想・技術であり、陰陽師は重要な技術の担い手だった。
奈良時代の陰陽師
飛鳥時代の陰陽師が、占い・風水などを駆使する「技術官僚」だったのに対し、奈良時代(710年~784年)以降、陰陽師は占い、風水に加え、「呪術宗教家」としての色を強めていくことになる。
これは奈良時代以降、日本に伝来し影響を強め始めた「道教」、「密教」の呪術的部分の広がりと、さらには「修験道」の始まりの影響によるものである。
「道教」は「神仙思想」を基本とする、中国古来のシャーマニズム的な信仰である。その究極的な目的は、修行によって心身を高め「不老長寿」、「仙人」になることである。
飛鳥時代に始まった「陰陽道」には、当然ながら「陰陽五行」だけでなく、この「道教」の教えも入っている。しかし飛鳥時代の日本においては、天皇こそが最高峰の存在であった。したがって仙人(神に近い高次の存在)になるための「仙術」を陰陽師たちが実践することは奨励されていなかったようだ。また、同じ理由により「道教」はその後も日本に定着しなかったとされている。
しかし奈良時代に入ると、「道教」の使い手である僧たちが一般市民の間に跋扈(ばっこ)し、さらに「道教」、「陰陽道」、「密教仏教」を基にした修行法である「修験道」を修める者らが現れ始めたのである。「修験道」は山篭りの修行を経て、呪術や超自然力を身に付けることを目的としている。
その開祖とし知られる「役小角」(えんの おづの/おづぬ /おつの:634年~701年)は、「流刑先から海を歩いて富士山に登った」他、その荒唐無稽とも思えるようなエピソードの数々からも、かなりの超自然力を身に付けていたであろうことが伝承されている。 こうした呪術や超自然力を身に付けた行者たちで、僧侶の資格を有する者を「法師陰陽師」と言う。宮廷陰陽師たちが、ひたすら朝廷に奉仕することに専念したのに対し、法師陰陽師たちは、その「呪術・超自然力」を携えて一般庶民たちに教えを説き、多くの支持を得ることになる。
こうした法師陰陽師たちの存在は、当然ながら朝廷にとっての脅威となる。というのも、法師陰陽師の中には、密かに貴族たちとつながり、吉凶を占うばかりでなく、場合によっては敵対者の呪殺さえ請け負うこともあったという。
こうした事態を重く見た朝廷と「陰陽寮」は、不穏な法師陰陽師を排斥しつつ、一方では、宮廷陰陽師たちにこれまで習得を推奨しなかった「呪術」、「妖術」、「仙術」など超自然力を身に付けていくことを解禁していくのである。
前述の修験道の開祖、役小角は、民衆を惑わした罪により、伊豆島へ流刑になる。この処分は、いかに朝廷が「道教」「修験道」行者たちの呪術や超自然的なパワー(現代で言う超能力)を恐れたかを示す好例と言えるだろう。ちなみに、後述する平安時代末期以降の陰陽師ブームの先駆け的な存在である「賀茂忠行(かものただゆき)」は、この役小角の子孫である。
また宮廷陰陽師からスパイとして役小角に弟子入りし、修験道のエッセンスを陰陽道に取り込むなどの工作も行われている。陰陽道はこのように、内外からさまざまに登場してくる思想や呪術のエッセンスを習合させながら独自体系を構築していくのである。
平安時代の陰陽師
平安期に入ると、陰陽師はより呪術的な対処術を身に付け、本格的な「呪術宗教家」を目指すことになる。その背景には、差し迫った大きな理由があった。それが平安時代(794年~1185年)に急速に広まった「御霊(ごりょう)信仰」である。
「御霊信仰」とは、疫病や天災を、死者、もしくは魔界からの怨霊による災い・祟りとし、それら「怨霊」を「御霊」(ごりょう)へと鎮めることで、厄災から逃れようとする信仰である。
平安時代に入り、人口増加に伴う都市化が進む一方で、洪水・地震などの自然災害、家屋の火災、疫病の発生、盗賊、殺人、なども頻発するようになる。また、さまざまな権力争いが勃発した平安時代においては、有力者の暗殺直後に疫病が蔓延するなど、「怨霊による厄災」を暗示させる事例が相次いだのである。
平安時代において陰陽師の社会的地位が、より頭角を現していくのは、こうした御霊信仰のニーズにマッチした対処術(占術、呪術、祭祀に関する知識)を有していたからである。その結果宮廷陰陽師は、ますます重用され、階級も上位に位置づけられていく。
また平安時代においては、貴族自身も陰陽道の教えを生活基盤としていた。当時の貴族の暗記項目が記された教科書だった「口遊(くちずさみ)」には、陰陽師の使う呪文も数多く収録されている。
この時代の陰陽師の霊能者的なテクニックの多くは、「道教」、「密教」、「呪禁道」などのメソッドに依拠したようだ。「道教」からは方術に由来する方違、物忌、反閇などの呪術が習得され、「密教」からは呪法だけでなく、空海がもたらせた「宿曜道」とよばれる占星術テクニックも習得の対象となった。また平安時代には、陰陽寮より古くからあった「典薬寮」が廃止になり、陰陽寮に統合されることになる。
これにより、「呪禁道」を修めた「呪禁博士」らの教えが陰陽師にも伝えられ、呪術による病気のコントロールという、シャーマン的な素養も加わっていくことになる。
平安時代を総括してみると、日本のスピリチュアル史においても、最重要な時代であることがわかる。これはこの時代において「神仏習合」が盛んになったこともその背景にある。祈りを中心とした神道系の精神的メソッドと、術を併せ持つ密教系仏教の物質的メソッドの折衷が、陰陽師たちの中において、より総合的なスピリチュアルパワーとして開花していくのである。
花形陰陽師の登場
平安時代の末期にあたる10世紀以降からは、陰陽師はより花形的存在となる。
それは主に、陰陽道・天文道・暦道のいずれをも究め、陰陽師にして陰陽頭(陰陽寮のトップ)というエリート出世を果たした「賀茂忠行(かものただゆき)生没年不詳」と、その弟子である「安倍晴明(あべのせいめい921年~1005年)」らの存在によるところが大きいと言えるだろう。
賀茂忠行は現代で言う「透視能力者」でもあったようだ。覆物の中身を当てる「射覆」、「占覆」が得意だった賀茂忠行は、醍醐天皇からその腕を披露するように命じられた。忠行の目の前には八角形の箱が目の前に出され、これを占った結果は「朱の紐でくくられている水晶の数珠」である事を見事的中させ、「天下に並ぶもの無し」と賞賛されたことが『今昔物語』に書かれている。
こうした賀茂忠行の発揮した偉才は、その血に修験道の祖である役小角のDNAが宿っているからとも言える一方で、陰陽師たちが修験道のメソッドなども取り込みつつ、時代のニーズに対応する形で、呪術力や超自然力の強化に全力を挙げた成果とも言えるであろう。
その賀茂忠行によって才能を認められたのが、現代の日本でもっとも有名な陰陽師である、安倍晴明である。安倍晴明の能力等の詳細に関しては別項で詳述する。ここでは、朱雀帝から一条帝までの六人の帝(朱雀、村上、冷泉、円融、花山、一条)に仕えた安倍晴明が、日本独特の陰陽道の大綱を確立させ、現代の我々が日常生活の基準とする年中行事や暦術、占法などを確立させた人物である、とするに留めておこう。
また「陰陽寮」における安倍晴明の最終役職は「天文博士」(天体観測から吉凶判断を行う:従四位下)である。また、安倍晴明と実力を伯仲させた法師陰陽師としては、安倍晴明のシンボル「セーマン」(五芒星)に対抗して、「ドーマン」(九字切り)をシンボルとした「蘆屋道満(あしやどうまん)」が有名である。
朝廷陰陽師において、賀茂忠行、安倍晴明らの能力がいかに突出したものだったかは、この後、明治維新後に「陰陽寮」が廃止されるまで、宮廷陰陽師の系譜が賀茂氏と安倍氏の末裔たちによる二大宗家によってほぼ独占されていくことからも明らかである。
鎌倉時代~室町時代の陰陽師
鎌倉時代に入ると武家社会が台頭するが、この時代はおいてはまだ、陰陽道は武家社会にも大きな影響力を持ち、陰陽師の存在も必要不可欠なものだった。というのも、多くの武将は戦において、占術による結果を信頼したからである。
したがって、公家に仕える宮廷陰陽師だけでなく、将軍家に仕える「武家陰陽師」もいたとされている。これら武家陰陽師たちには「軍師」としてのミッションが加わることになる。「軍師」とは、参謀である。戦においては、それを仕掛けるタイミング、方位、攻め方、すべてにおいて戦術が必要となる。その戦術策定において、陰陽道や「遁甲(とんこう)」と呼ばれる兵法の奥義を知る陰陽師の力が必要とされたのである。
また鎌倉時代以降、「忍術・武術・諜報術」に長けた存在である「忍者」が登場する。この忍者が活用する術は、山伏の修験道、密教などが基盤となったものである。忍者育成においても、武家陰陽師の暗躍があったと思われる。時には民間陰陽師もしくは修験道系の法師陰陽師自身が、忍者へと姿を変えた場合もあったであろう。
室町時代に入ると、宮廷陰陽師の本格的な公家化が起こる。室町時代中期、安倍氏は天皇よりが「土御門家(つちみかどけ)」の称号を賜り、以降、安倍氏系譜の陰陽師は「土御門」を名乗り、公家の家格のひとつである堂上家に格上げされる。これにより、土御門家はまだ安泰な環境を得られていたのであるが、その他多くの陰陽師にとっては、「応仁の乱」(1467年)に端を発する戦国時代に入ると、受難の時代の始まりとなる。
戦国時代から安土桃山時代の陰陽師
戦国時代に入り、陰陽道と陰陽師擁護派だった将軍足利義政の権力が衰えると、宮廷陰陽師は生活に困窮するようになる。陰陽師の重要な収入源のひとつに、「祭祀の執行」があるが、この戦国時代は陰陽道の祭祀はほとんど行われなくなるのである。また陰陽寮は土御門家と一部賀茂氏の寡占状態で、多くの陰陽師を雇う余裕は無いという状況である。
一時期は土御門家と勢力を争った賀茂氏はその後、庶民において需要のあった暦作りで食いつなぐも、1565年、陰陽頭だった賀茂在富の死をもって陰陽師の歴史からその名前が消えることになる。
また応仁の乱後の混乱は、陰陽道の歴史において、致命的ともいえる打撃を与える。それが武家による土御門家の所領侵略である。これにより土御門家が保存してきた、陰陽道の多数の典籍や重要資料などが散逸する。さらに所領からの税収難や優秀人材不足などが折り重なり、本家の土御門家でさえも凋落の兆しを払拭できなくなっていくのである。
「戦国時代」において、陰陽師が没落していく背景には、武家社会の精神基盤の変化が色濃く影響を与えている。室町時代から広がり始めた「禅宗」は質素・慎み深さを重んじるもので、特に戦国時代の武家社会とは親和性が高かったと考えられる。
また宮廷陰陽師の重要な仕事のひとつに「京暦作り」(太陰太陽暦)がある。しかし織田信長の時代に、陰陽頭の土御門久脩と暦博士の賀茂在昌(賀茂在富の子息)が作成した京暦に不備(日食・月食期日の誤り)があることを信長から指摘され、こうしたことも武家の陰陽師不信に一役買うことになる。
一方、ミスを犯した賀茂在昌はキリスト教と共に入ってきた西洋暦学である太陽暦と天文知識にも魅了され、キリスト教に入信し賀茂家から破門され陰陽寮を去る。
「安土桃山時代」の豊臣秀吉はさらに、陰陽師に対する不信感を強め、最後の砦ともいうべく土御門家の排斥措置を断行する。この措置によって宮廷陰陽師が再び活動ができるのは、徳川幕府の誕生を待つことになる。
また、民間においても、陰陽師に対するイメージは悪化する傾向を見せていく。その背景には、法師陰陽師と民間陰陽師の活動の自由化に起因していると言える。戦国の世になると、比較的朝廷からの監視も緩み、一般市民に対する法師陰陽師の活動は自由になる。
しかし、民間に跋扈した法師陰陽師の中には、「エセ自称陰陽師」も多数いたと見られる。天皇や貴族を相手に、インチキはできずとも、民間相手であればいくらでも詐欺が可能と言うことだったのだろう。今で言う、インチキ霊感商法ビジネスも流行り、その結果、陰陽師へのイメージが悪くなり始めるというデメリットを被ることになる。
こうして日本が安定期を迎える「江戸時代」へと向かう歴史の中で、陰陽師の社会的地位や信頼は、徐々に失われていくようになるのである。
江戸時代の陰陽師
江戸時代に入ると、徳川家の幕府による統治時代が始まる。これにより宮廷陰陽師の本家、土御門家は再び陰陽寮へと戻ることになる。しかし、陰陽師や陰陽道が、かつてのように政治的に重視されたわけではない。従って、陰陽寮は存続するものの、そこにはもはや多数の陰陽師を必要とする理由がない。一方で、幕府においての陰陽師は「寺社奉行」の管轄としての配置になるが、そのポストも数は限られている。そこで多くの陰陽師たちは、それまでの在野の法師・民間陰陽師たち同様に、市井の人たちに向けた活動で生計を立てる必要性に迫られるわけである。
こうして陰陽師の民間化が加速する中、17世紀末になると、「土御門家」が民間陰陽師たちに免状を与える権利を独占することで日本の陰陽道と陰陽師の支配権を獲得する。
その結果、出没していたインチキ陰陽師の排斥には一役買い、江戸時代は市民の間で陰陽師人気が再び高まったようである。その背景には、これまで陰陽道の教えのエッセンスが、朝廷内において封印されていたということもあるだろう。そのため、かつて朝廷が陰陽師を重用したように、江戸時代以降は民間において、陰陽師が頼られ、暦や方角の吉凶を占う民間信仰として陰陽道が広く日本社会へと定着していく。
明治時代から現代の陰陽師
明治時代に入り新政府が誕生すると、陰陽師と陰陽道は、再び排斥化の傾向が強まっていく。
その背景には大きく三つの理由があった。ひとつは「天皇親政、国家神道の強化(神仏分離)」である。これまで陰陽師はその特異能力により、天皇にさまざまなことを進言する存在だった。しかし、明治以降は、「陰陽師ごときが天皇にものを申すことはまかりならん」という風潮が強まると同時に、神道でもなく仏教でもない陰陽道は不要であり、「国家神道」を重視すべきという意見が強まった。
二つ目は「太陽暦」導入による西洋化の波である。事実上、最後の土御門家陰陽道の当主だった土御門晴雄(1827年~1869年)は、太陽暦導入に反対したが、この反発は逆に明治政府の陰陽寮、陰陽道、陰陽師排斥化の勢いを強めるだけだった。
そして3つ目が、「富国強兵、殖産興業」の波である。開国後に西洋の近代科学に触れた明治政府にとって、「呪術や占術」をエッセンスとする陰陽道はもはや、非科学的迷信としか映らなかったのである。
この結果、土御門晴雄の死の翌年に当たる明治3年(1870年)、陰陽寮は廃止されてしまうのである。さらには明治5年(1872年)、新政府は陰陽道をも迷信として廃止させたのである。
これにより、宮廷陰陽師、民間陰陽師のすべてを統括していた「土御門家」もすべての権限を剥奪され、多くの陰陽師たちは活躍の場を失うことになる。
「土御門家」は福井県に本庁を置く「天社土御門神道(てんしゃつちみかどしんとう)」という形で存続するが、陰陽道色は打ち出せないため、古神道を中心とした教えに転じる。
陰陽道・陰陽師が再び、神社を拠点としての活動、もしくは民間での占い師としての活動が可能となるのは第二次大戦後のことである。敗戦により、旧明治法令・通達の廃止にともない、陰陽道を禁止する法令も公式に廃止される。
これにより一部の神社では、再び陰陽師が神職として祈祷等を行うようになった。また、神社所属ではなく、一般占い師として、占い・除霊・浄霊、風水、物品販売等を行っている者も現代には存在している。
しかしかつてのように、陰陽道の呪術体系をも駆使する陰陽師の存在は皆無であろう。というよりも、文献資料や陰陽寮という陰陽師の管理・育成機関を喪失した今となっては、陰陽道の叡智を体系的に身に付けること事体がもはや不可能に近いのである。大和朝廷以来長い年月に渡り、日本の精神・思想・政治・学術基盤ともなった陰陽道、そしてその担い手である陰陽師は、総本山的な拠点を失ったまま現在に至っているのである。
《あ~お》の心霊知識
- 悪魔
- アカシックレコード
- 悪霊
- アストラル体
- アストラル投射
- アセンション
- アマビエ
- アミュレット
- アメジスト
- アラクネ
- アリソン・デュボア
- アンビリカルコード
- 異界
- 生霊
- 意識体
- イタコ
- 稲荷神
- 稲荷と霊障
- 祈り
- 因果応報(カルマの法則)
- 因縁
- 丑の刻参り
- インチキ占い師
- 占い師
- 運勢
- エクソシスト
- エクトプラズム
- エドガー:ケイシー
- エネルギーワーク
- エネルギー体
- 江原啓之
- 遠隔ヒーリング
- 遠隔透視
- 縁起物
- エーテル体
- オカルト
- 御教
- 恐山のイタコ口寄せ
- 織田無道
- オーブ
- お札
- お守り
- お守り2
- おみくじ
- 音楽療法
- 陰陽師による除霊-呪文-儀式
- 陰陽師の歴史
- 陰陽道-陰陽師
- 近代の陰陽師
- 歴史に残る陰陽師
- 怨霊
- お寺
- お焚き上げ
- オーラ
