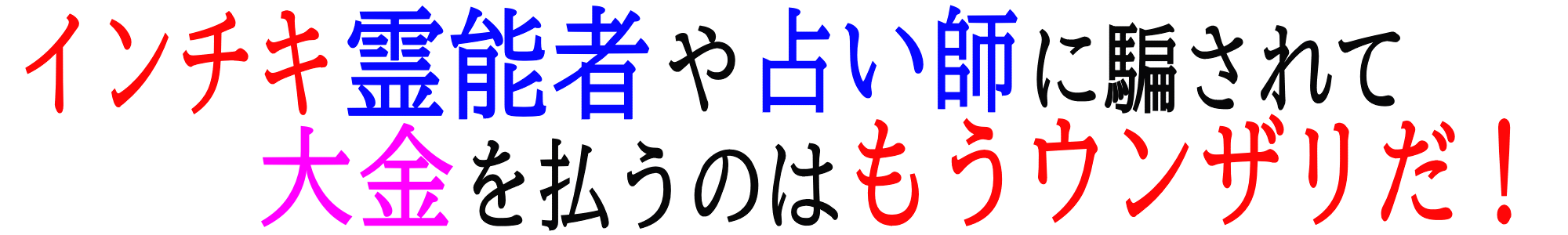


縁起物
縁起物とは、神道や仏教など、日本における宗教宗派の教義が起源となり、「招福祈願」、「厄除祈念」「五穀豊穣」、「商売繁盛」、「家内安全」、「無病息災」、「子孫繁栄」、などを目的とした物・人・文化風習である。
縁起物には、「物的縁起物」、「人的縁起物」、「文化風習的縁起物」などがある。
「物的縁起物」は主に、社寺や市などで販売もしくは授与される物品で、破魔矢・破魔弓、絵馬、おみくじ、招き猫、七福神、宝船、だるま、熊手、羽子板、朝顔、ほおずきなど様々にある。
社寺で行われる祭礼において使われる「神輿」「山車」などや、神社において、「依り代・結界」となる、注連縄(しめなわ)、門松、お飾り、榊(サカキ)も縁起物である。
また、滋養強壮、長寿の目的で食べられる食品や薬事効果を期待して食される、おせち料理、七草粥、鰻、初鰹、年越し蕎麦などの旬物も縁起物とされる。「人的縁起物」は主に社寺が行う祭礼において、「福男・福娘」などに選ばれた人や力士などである。なぜかというと、神道において、これらの人物は「神の依り代」と考えられているからである。
「文化風習的縁起物」とは、時節に行われる伝統文化に起因するものである。
例えば正月に行う、福笑い、羽根突き、独楽廻し、凧揚げといった遊び、お年玉、福袋も本来は縁起物である。
また、こいのぼり、武将人形・兜、七夕、お盆(日本古来の祖霊祭り)、月見、七五三などの行事、結納、節分およびそれにまつわる物品等である。
縁起物のルーツと七福神
日本における縁起物が多種多様になっている背景には、日本(神道、仏教、密教他)、中国(仏教、道教他)、インド(ヒンドゥ教)などの、さまざまな宗教的要因が日本において習合されてきた経緯がある。
縁起物のひとつである「七福神」は、その習合要素が集約されたものといえるだろう。
- 七福神:福をもたらすとして日本で信仰されている七柱の神
- 恵比寿:「大漁追福」の漁業の神であり、「商売繁盛」や「五穀豊穣」をもたらす、商業や農業の神。
- 大黒天:ヒンドゥー教のシヴァ神と日本古来の大国主命の習合。大黒柱と現されるように「食物・財福」を司る神。
- 毘沙門天:ヒンドゥー教のクベーラ神が起源で、仏教の神のヴァイシュラヴァナ(多聞天)となり、日本では毘沙門天と呼ばれる。
- 弁才天 (弁財天):七福神の中の紅一点で、起源はヒンドゥー教の女神サラスヴァティー。
- 福禄寿:道教の宋の道士または、寿老人の別名または同一神。
- 寿老人:道教の神で南極星の化身の老子。
- 布袋:唐の末期に実在したといわれる仏教の僧。
縁起物としての力士
不祥事が相次ぐ相撲界であるが、それでも依然、国技として相撲を保護しようとしていることに疑問を抱く人は多いのではないだろうか。なぜ相撲が国技かといえば、相撲は神道の儀式・秘儀が様々に集約されたものだからである。それは土俵作りに始まり、力士の番付や土俵上で行われる様々な儀式、行司の格好や存在価値など、あらゆる面において相撲は神道儀式の現れである。
つまり神道儀式・秘儀を、相撲というスポートにして、国民に浸透させることが重要なのである。これが不祥事が相次ぐ相撲界ではあるものの、国技から外せない理由である。
古来において相撲とは、相手と戦うものではなく、「一人相撲」がその原点である。では誰と組みすのかといえば、相手は神である。
つまり、相撲における力士とは、神社における御神木と同じで、神が依り代(降臨)とする選ばれた人間、なのである。しかし現代の力士たちが、こうした認識を持っているかどうかは定かではないが、これらの理由により力士たちは本来、縁起物とされてきたのである。
意外と知られていない縁起物
生活に入り込んだ物にもたくさんの縁起物がある。 意外と知られていない縁起物をいくつか紹介しておこう。
ちらし寿司
元々ちらし寿司は五色の具材で構成され、これは宇宙を表わしたものだった。そのうちの4色は、中国における四神「天の四方の方角を司る霊獣、東の青竜(せいりゅう)・南の朱雀(すざく)・西の白虎(びゃっこ)・北の玄武(げんぶ)」を表現し、同時に四季を表わした縁起物とされていた。
狐の嫁入り(天気雨)
本来の「狐の嫁入り」とは、死者の出る予兆として忌み嫌われるものである。しかし天気雨も「狐の嫁入り」と表現され(県によって異なる)、この場合は「狐の祝言」として縁起物と考えられてきた。
天寿
よく宿命を生き切る事を「天寿をまっとうする」と表現する。しかし天寿が何歳を意味するか知る人はあまりいないようである。天寿とは「250歳」を意味する言葉である。このように歳を重ねる行為自体も縁起物であり、その歳毎にお祝いが行われる。
主に以下のものである。
還暦(60歳)、喜寿(77歳)、傘寿(さんじゅ80歳)、半寿(81歳)、米寿(88歳)、卒寿(そつじゅ90歳)、白寿(99歳)、百寿(100歳)、茶寿(ちゃじゅ108歳)、大還暦・昔寿(せきじゅ120歳)、天寿(250歳)。
ちなみに言葉上の最高齢は「麦寿」(ばくじゅ)で、「9002歳」である。これらの多くは中国の伝承に起因している。道教は神仙思想であるが、仙人と化した人間はもしかすると、「天寿」はおろか、「麦寿」まで生きるのかもしれない。
《あ~お》の心霊知識
- 悪魔
- アカシックレコード
- 悪霊
- アストラル体
- アストラル投射
- アセンション
- アマビエ
- アミュレット
- アメジスト
- アラクネ
- アリソン・デュボア
- アンビリカルコード
- 異界
- 生霊
- 意識体
- イタコ
- 稲荷神
- 稲荷と霊障
- 祈り
- 因果応報(カルマの法則)
- 因縁
- 丑の刻参り
- インチキ占い師
- 占い師
- 運勢
- エクソシスト
- エクトプラズム
- エドガー:ケイシー
- エネルギーワーク
- エネルギー体
- 江原啓之
- 遠隔ヒーリング
- 遠隔透視
- 縁起物
- エーテル体
- オカルト
- 御教
- 恐山のイタコ口寄せ
- 織田無道
- オーブ
- お札
- お守り
- お守り2
- おみくじ
- 音楽療法
- 陰陽師による除霊-呪文-儀式
- 陰陽師の歴史
- 陰陽道-陰陽師
- 近代の陰陽師
- 歴史に残る陰陽師
- 怨霊
- お寺
- お焚き上げ
- オーラ
