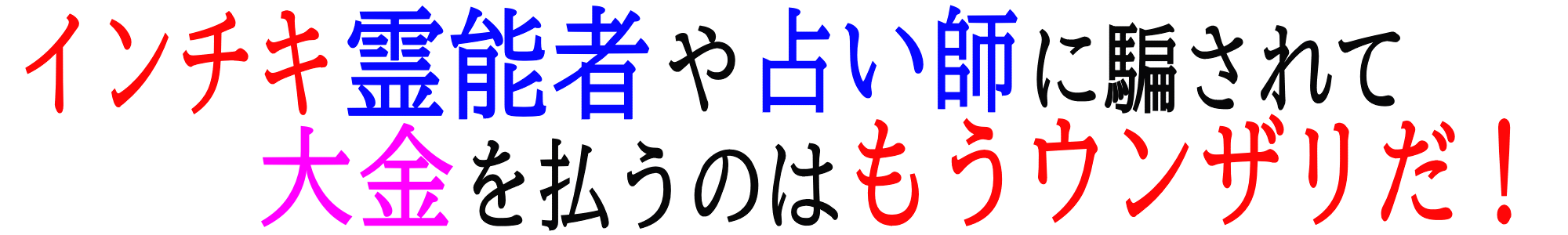

コックリさん
「コックリさん」とは、日本における霊的交信の一種であり、特に昭和後期から平成初期にかけて、小中学生の間で流行した降霊術の一形態です。西洋の「ウィジャボード(Ouija Board)」に類似したものですが、日本独自の文化的背景や信仰と結びつき、特有の儀式として発展しました。
1. 「コックリさん」とは? その起源と歴史
「コックリさん」は、文字の書かれた紙と硬貨を用いた簡易的な降霊術です。参加者が硬貨に指を置き、質問をすると霊が降りてきて回答するとされます。
(1)「コックリさん」の語源と発祥
「コックリさん」の名称には諸説ありますが、最も有力なのは 「狐(コ)、狗(ク)、狸(リ)」 という動物霊を指す説です。これらの動物は、日本の民間信仰で霊的な存在として崇められ、特に狐は稲荷神の使いとして信仰されています。
起源については、明治時代に流行した「テーブル・ターニング(机動かし)」や西洋のウィジャボードが元になったと考えられています。
(2)大正・昭和時代の流行
明治時代末期から大正時代にかけて、日本では「こっくりさん遊び」として広まりました。その後、昭和時代には学校の怪談文化と結びつき、都市伝説の一部として認知されるようになりました。
特に1970年代から1980年代にかけて、子どもたちの間で急速に流行し、オカルトブームの影響も受けて 「絶対に最後までやらないと呪われる」「途中で止めると霊が憑く」 などの警告が付随するようになりました。
2. 「コックリさん」のオカルト的背景と儀式
「コックリさん」は単なる遊びではなく、霊的交信の一形態とされ、参加者の霊的状態や場のエネルギーによっては、本物の霊的現象が起こることもあると言われています。
(1)儀式の流れ
「コックリさん」の基本的なやり方は次の通りです:
1. 紙の準備
- 「はい」「いいえ」「五十音表」「鳥居の絵」などを書いた紙を用意。
2. 硬貨の使用
- 10円玉または5円玉を用意し、参加者全員が指を軽く触れる。
3. 招霊の儀式
- 「コックリさん、コックリさん、おいでください」と唱える。
4. 質問と回答
- 参加者が質問し、硬貨が動いて答えを示す。
5. 終了の手順
- 「コックリさん、お帰りください」と唱え、硬貨が「鳥居」の上に移動するまで待つ。
この手順が適切に行われない場合、「コックリさんの霊が残留する」とされるため、特に注意が必要とされています。
(2)動物霊との関係
日本の伝承では、「狐・狗・狸」などの動物霊が人に取り憑くことがあり、特に狐憑きは民間信仰の中で有名です。「コックリさん」の正体がこれらの動物霊であるとする説もあり、軽い気持ちで行うと霊障を引き起こす可能性があるといわれます。
3. 「コックリさん」の霊的危険性
「コックリさん」は、多くの霊能者やオカルト研究者から「安易に行うべきではない」と警告されています。その理由をいくつか挙げます。
(1)正体不明の霊との接触
降霊術では、誰が降りてくるかをコントロールすることは難しいです。善良な霊が応じる場合もあれば、低級霊や悪霊が入り込むこともあります。
また、霊が嘘をつくケースも多く、最初は優しく応じても、次第に不吉な言葉を発したり、参加者に悪影響を及ぼすことがあります。
(2)未浄化霊による憑依現象
「コックリさん」を行った後に、以下のような症状が現れることがあります:
- 異常な倦怠感や頭痛
- 急な感情の変化(怒りや悲しみが強くなる)
- 幻聴や幻視の発生
- 特定の場所で気分が悪くなる
これは、セッション中に未浄化の霊が参加者に取り憑いた結果と考えられます。
(3)呪いの媒介
「コックリさん」は時に「呪い」の道具としても利用されます。例えば、特定の人物の名前を出して悪意を向けることで、霊的な影響を及ぼすケースもあります。
4. 心理学的・科学的視点からの「コックリさん」
霊的な観点とは別に、心理学や科学的な視点からも「コックリさん」の現象は説明できます。
(1)「イデオモーター効果」
科学的には、「コックリさん」の動きは 「イデオモーター効果(無意識の筋肉運動)」 によるものと説明されます。
- 人間の脳は、期待した通りの動きを無意識に引き起こすことがある。
- 参加者が「硬貨が動く」と信じていると、無意識のうちにわずかな力を加えてしまう。
これにより、実際には誰も意識的に動かしていないはずの硬貨が勝手に移動するように感じるのです。
(2)「集団心理と暗示の影響」
複数人で行うと、集団心理によって暗示が強まり、「霊が動かしている」と信じやすくなります。特に恐怖心があると、脳は実際には存在しない現象を補完してしまうことがあり、これが「霊的体験」として記憶されます。
5. 「コックリさん」とどう向き合うべきか?
「コックリさん」は単なる遊びではなく、霊的・心理的に強い影響を及ぼす可能性があります。
- 興味本位で行わない。
- 霊的な知識がないまま試さない。
- 絶対に途中でやめない。
- 体調が悪くなったらすぐに浄化を行う。
オカルト研究者や霊能者の立場からも、「コックリさん」は軽々しく行うべきものではないと強く警告します。慎重な対応が必要です。
