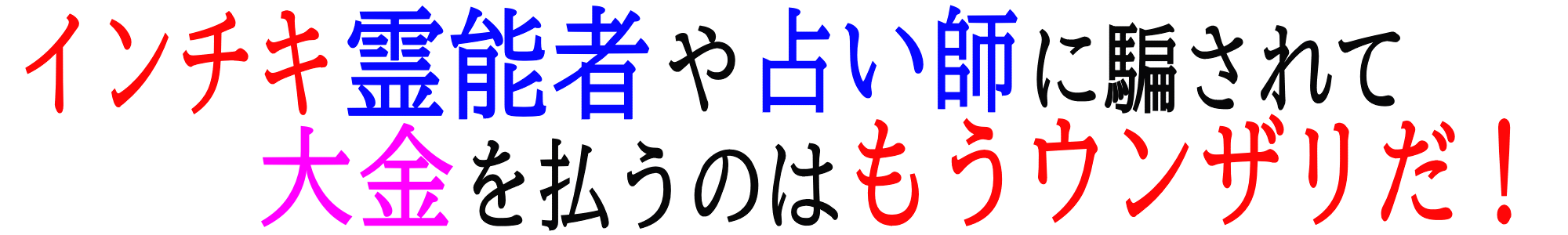



輪廻
りんねと読み、サンスクリット語のサンサーラ(流れるという意味)の訳である。インド古来に発展した思想。
辞書『大辞泉』によると『生ある者が迷妄に満ちた生死を絶え間なく繰り返すこと。三界・六道に生まれ変わり、死に変わりすること』とある。簡単に言うと人が何度も生まれ変わることで、生まれ変わるのは、人だけでなく動物など生類を含める。
仏教用語で、ヴェーダや仏典などに見られる。「業」の思想と切り離せない思想・概念である。流転、転生、輪転ともいう。
読みは、「りんえ」の連声(れんじょう。つの語が連接するときに起きる音変化)による。
無限に転生する様子をぐるぐるまわる車輪にたとえたことから、漢字の輪廻があてられた。
インドの輪廻
輪廻「サンサーラ」は、前世での行為(業。善悪どちらの行為も指す)によって、環境や経験や寿命などが多様に異なる生存として生まれ変わることである。
インドではこの限りない生と死の繰り返しである輪廻の生存を苦しみとし、輪廻から解放されることを最高の理想として目指す。輪廻からの解放を解脱といい、ほとんどのインドの宗教・哲学の目指すものとなっている。
ヒンドゥー教
輪廻はヒンドゥー教に発展する前のバラモン教であった当初、「五火」と「二道」の説として登場し、輪廻という用語ではなかった。『五火二道説』という文献もある。これらはまだ断片的なもので、バラモン教最初期のウパニシャッド文献と最終期のブラーフナ文献に見られる。
五火とは、人間が死に再びこの世に生まれ変わるまでの過程を5つの祭火になぞらえたものである。5つの祭火とは、死者は「月に一旦、留まる」、「雨になって地に降って戻る」、「植物に吸収され穀物になる」、「それを食べた男の精子となる」、「それが性交により女の胎内に注ぎ込まれ胎児になって、再び誕生する」、までの過程である。
二道とは、人間の転生は業によって2つに分けられるとするもので、「神々の道(解脱への道。もう再生しない)」と「祖霊の道(輪廻への道。再生する)」である。この、「祖霊の道」が輪廻である。
この五火二道の思想が、いろんな思想家や、他宗教(ジャイナ教や仏教など)の影響も受けた集大成がヒンドゥー教の輪廻観となる。
そして信仰心と業によって来世が決まる、というのが教義のベースとなったことで、カースト制度の位階ができた。
業(行為)を行ったの後には、なんらかの結果が現れる。
この結果は、業の後に即時反映する事柄だけでなく、次の業とその結果にも反映される。業は、それが終わった後でも影響力を残し、死んだ後でまた生まれ変わろうとも前世の業の影響下で結果がもたらされる。ゆえに輪廻の原因は前世の業にあり、生まれ変わったときの生は前世によって決定される。
業を超越する段階に達しなければ永遠の生まれ変わりから解放されることはない。
よく因果応報というが(善因楽果、悪因苦果、自業自得ともいう)、これは業にもとづくものである。
輪廻の思想と結び付けて高度な理論により、インドの死生観・世界観を発展させていった。
仏教
輪廻の完全な概念はゴータマ・ブッダが初めて持ったという。
仏教では、物事には原因と結果があるという因果論を原則としていて、「業」論にもとづき、個別の人生に対しても輪廻思想を前提にして考える。
仏教における輪廻とは、苦しみ多き世界である現世を六道(天界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界)とし、死後は六道をまわり続けることを言う。
そして、現世の苦しみからの解脱(極楽世界に行くこと)を目的とし、善行をすすめている。
インドの宗教ではアートマンと言って魂は永遠不滅とするが、それとは異なる点として仏教においては、永遠不滅の魂つまり主体的な我というものはない。これを「無我」という。つまり「空」の概念にもとづく考え方である点が他のインド宗教と大きく異なる。
なお、当時のインド社会にあった輪廻思想に基づいて説いたとし仏教においての輪廻自体は否定する立場もある。
仏教では、無我が前提でなければ輪廻転生が存在し得ないとする。輪廻に永遠(=主体、我、アートマン)があるならば、永久に輪廻状態である「常在」論か、そもそも輪廻することなく死後は存在が停止する「断滅」論に陥ると考える。つまり主体である「我」が存在する場合、恒常か無常のどちらかである。だが、恒常であるなら永久に輪廻を続け解脱することはなく、無常であるなら輪廻は成立しない。ということは、永遠の魂である主体そのものを否定する立場「無我」によってしか、輪廻を説明することはできない。
ブッダ以前のインド思想家たちも輪廻の概念を曖昧にもっていたが(ただし、ウパニシャッド文献において記述がないことから、当時、バラモン教には輪廻の概念はなかったと見る)、それをブッダは十分としなかった。
仏教では変化しない物体を一切認めず、それをすべての生命について言えば魂や神というような「本体」を認めないということっである。
なので、仏教における輪廻とは、物質的で説明できる話ではない。「識(認識するはたらき)」の移転であると言える。「識」の連続についた仮の名前が「心」である。ゆえに永遠の魂や主体や我とは、本体のない識の連続であり、つまり錯覚のようなものに過ぎない。だから、輪廻において魂は否定される、無我である。
輪廻の経過
死後、「識(認識するはたらき)」が消滅したあと、別の場所にて新しく類似の「識」が生まれ、それらは別物であるが、流れとして一貫性をなす。世代から世代へ識(意識)を伝達すると言えばわかりやすいだろうか。
生きているうちにも識は現れ消え続ける。仏教における輪廻とは、単なる死後を説いているだけではなく、心のはたらきを説明する概念でもある。
輪廻思想の発展
輪廻思想がみられる最古層の経典たち……ダンマパダ、スッタニパータ。 ダンマパダは単純に二元化されており、スッタニパータは地獄について具体的である。
部派仏教の時代……世親の『倶舎論』。五趣の輪廻の説が見られ、生命は、この五趣を輪廻するとした。五趣はのちに六道と称されるようになる。
後代、大乗仏教の時代……六道に加えて十界を立てる。自らの意思で転生先を支配できるとし、縁覚・声聞・菩薩・如来としての境遇を想定した。
その他
古代ギリシアでは一部的に輪廻のような発想があった(オルペウス教、ピタゴラス教団、プラトンなど)。
しかし、西洋の感覚では時間は直線的に進むものであり、輪廻のようにめぐる感覚はなく、ゆえに伝統的な教義に輪廻はない。
また、欧米キリスト教圏から振り返って見れば人間を他の動物と区別しない感覚は異端である。
ただ、キリスト教文化圏内においても、リンカネーション、という生まれ変わりの概念が存在する。たとえば広義の神秘学では教義として輪廻的な発想が多く見られ、信奉者も多い。起源が明確というわけではないが、やはり比較的新しい教義である。
