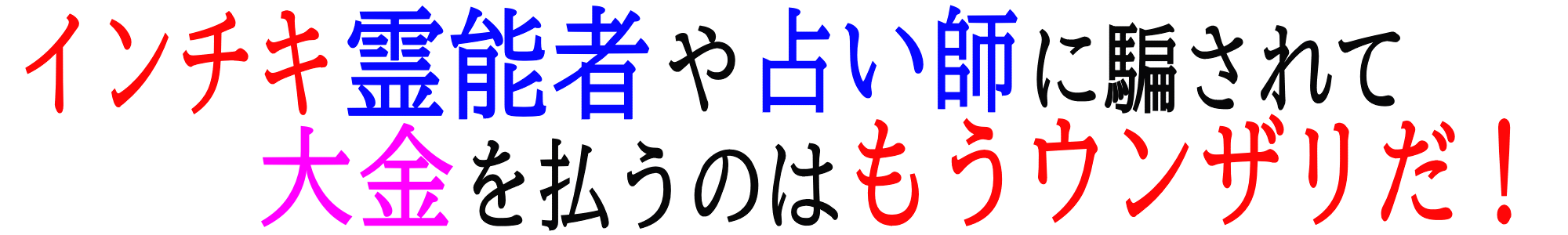



哲学
哲学とは、世の中のさまざまな物事について、その根本的な原理や真理を追究・探求することを目的とした学問の一分野のことを指す。
しかしながら、哲学は、ほかの多くの学問分野とは決定的に異なる特徴を有している。その名称からだけでは、どのようなことについて研究する学問であるかが明示されていないという点だ。
たとえば「経済学」なら経済を研究する学問だとわかるし、「英文学」や「生物学」や「経営学」なども同様である。「マンガ学」や「マス・コミュニケーション学」のような、比較的新しい研究分野でもこの原則は踏襲されている。哲学だけが、その研究主題が曖昧で不透明なのである。
といって、「臨床心理学」などのように、方法論から導き出された名前でもない。哲学は、その方法にも共通項は見当たらない。
日常生活のなかで疑問に感じたことについて、従来の常識や通念にとらわれることなく、思うまま自由に考えをめぐらせること。これが哲学である。
たとえば「生きるとはなんなのか?」、「世界とはなんなのか?」、「幸福とはどういうことなのか?」などなど、根本的で根源的な、ときとして幼稚にさえ思われるような疑問を、疎かにすることなく突き詰めようとする態度こそが、哲学の本質なのである。
すなわち、哲学を規定するものは、研究する際の態度だけであるといえよう。
哲学は概念的思考を必要とされる学問であり、知の学問ともいわれる。
「哲学」という用語の発生と定義
「哲学」という言葉は、明治時代初期に哲学者・西周が英語の「philosophy」(フィロソフィー)の訳語としてつくった言葉である。
この学問は、江戸時代までは「窮理学」、明治維新後は「理学」などと呼ばれていた。西が「哲学」という造語をはじめて用いたのは、1874年の『百一新論』という著作のなかでだった。その当時、西は政府でも有数の強い影響力をもつ知的指導者であったため、この造語が文部省に採用され、一般化されるようになったのだった。
ちなみに、西はほかにも「主観」、「客観」、「概念」、「命題」、「帰納」、「演繹」、「理性」、「現象」、「否定」、「観念」などなど、哲学関連の多くの用語を日本語に翻訳・紹介したことでも知られている。
訳出元である「philosophy」は、もともと古代ギリシャ語の「φιλοσοφ?α」(ピロソピア)から由来しているものだ。これは、「φιλοσ」(=「愛」)と「σοφ?α」(=「知恵」)が結びついた語であり、「知を愛する」という意味になる。本来は、現在でいう哲学にかぎらず、学問全般について指す言葉であった。まだ科学の発展が不充分で、学問が未分化であったからである。当時は自然科学も含めあらゆる学問が純粋な知の追究だった。
知を愛する学問なのだと考えれば、冒頭で述べたような学問としての曖昧さも理解できよう。知ることの欲求を追究し続ける学問だともいえる。
英語の「philosophy」をはじめとして、欧米諸国では音をそのまま転写することで「φιλοσοφ?α」に対応する語をつくってきた。イタリア語の「filosofia」、フランス語の「philosophie」、ドイツ語の「Philosophie」、ロシア語の「философия」などがそれに当たる。
他方で、中国では日本語の「哲学」を輸入して使ってもいる。
なお、現在わが国では、「人生観」のような意味に転用されて「哲学」という語が用いられるケースも目立つ。
哲学を専門的に学んだ者以外からは、哲学というと「なにか難しくてわけのわからないもの」といった印象が強く、こちらの意味での「哲学」のほうが身近に感じる場合もあるかもしれない。
これは、本来の学問としての哲学とはかけ離れた用法であるが、「人生哲学」の意味だと捉えれば、必ずしも誤用とは言い切れない。経験や試行錯誤から導き出された思想という意味では、たしかに哲学の一種ではあるだろう。
しかし、いたずらに混乱を招く用法であることも事実であるため、「哲学」の二文字を見たときにはその言葉の捉えかたをよく注意してみる必要があるだろう。
哲学の歴史と、その扱う対象
哲学の発祥は、紀元前7世紀ごろの古代ギリシャであるとされている。
はじめは、その研究対象は自然だった。人間が生活を営むうえで、自然ほど脅威となるものはなかったからだ。雨が降ったり風が吹いたりといった現象がなぜどのように起きるのかなど、科学が発達する以前はこれらが大きな疑問であったわけである。
現代の哲学の礎ができたのは、ソクラテスが登場してからだった。ソクラテスおよび、その弟子のプラトン、孫弟子のアリストレスなどは、哲学的探求の対象を自然ではなく、人間に求めた。
有名な「よく生きる」という言葉に代表されるように、いかによい人生をおくるか、そのためにはなにをすればよいか、といったことを追究するようになったのであった。現在用いられる「哲学」という言葉はこの意味である場合が多いだろう。
その後、キリスト教が浸透し強大な力をもった中世ヨーロッパにあっては、神が哲学の対象となったが、その時期が過ぎるとやはりソクラテスへ立ち返り、人間自身について知ろうとすることが哲学の中心になった。
哲学史上でも有名な、合理論(=「人間は理性的認識により真理を把握しうる」とする立場)と、経験論(=「人間は経験を超えた事柄については認識できない」とする立場)との対立があったのはこの時代である。
さらに時代が下り、近現代になると、先進諸国の経済はより安定し、高度な文明をもつようになった。寝食に困らない人々が増えたことで、よけいに「生きる」ことや「そこに存在する」ことの意味が問われるようになり、実存主義の立場が台頭した。
このように、哲学はその歴史上でも、扱う対象が統一的であったことはない。極端にいえば、疑問さえそこにあれば、世のなかのいかなる事象であろうとも哲学の対象となりうるということである。
このことは、ヨーロッパ哲学とまったく独立して、インドでも古代よりインド哲学が発達していたことから窺える。人間が存在し、文化があるところには、必ず哲学が生まれるということがいえよう。
一方で、最初期に研究対象であった自然は、現在では哲学の対象となることはめったにない。これは、科学の発展によって自然現象に論理的な説明がつくようになってしまったためである。すでに解決し万人が納得する答えが出た問題は、哲学にはならないのだ。
いわば、すべての哲学は仮説だともいえ、仮説だからこそより深く追究することを求める学問なのである。
なにが哲学であるか?(なにが哲学でないか?)
ここまで述べてきたように、あらゆる分野が哲学の対象となるため、哲学はさまざまな研究分野と部分的に関連している。
もっとも、哲学以外の学問であっても、ほかの分野と重なっている部分があるのはふつうである。だが、その場合は、それぞれの領域が定まったうえで一部分が重なっているというパターンがほとんだ。
哲学の場合はそれと異なり、領域自体が曖昧であるため、重なっているというよりも点在しているというほうが適切だろう。
日本の大学では、哲学を学ぶ場合は一般的に文学部のなかの哲学科で学ぶことになる。
これは、歴史上の著名な哲学書が文学作品としてあつかわれたり、古代の哲学者がしばしば詩人の肩書きももっていたことによるものである。
また、論理学が伝統的に哲学の一分野として扱われてきたこととも関係があるだろう。「正しさ」を追究する学問はたしかに哲学的である。
だが、海外の大学では独立した哲学部をもつものも少なくない。領域が広範にわたりすぎているためである。
現在でこそ哲学は文系として括られるが、最初期の哲学の対象が自然科学であったことからも、定義の困難さが窺えよう。
▼自然科学と哲学
たとえば、「時間」の概念は人間の文化に密接にかかわっているものであるため、しばしば哲学の研究対象となる。
だが、これは物理学的な研究対象でもある。同じものを対象にしていながら、それぞれのアプローチの方法はまったく異なるし、それぞれが追究しようとしているものも違うことが多い。
よって、物理学者が、哲学的な時間の捉えかたを自身の研究に援用することはまずありえない。ところが、哲学では必要に応じて数式を用いることもある。
これは、哲学と自然科学のスタンスの差からくるものである。自然科学では、実験を繰り返し重ね、そのなかから得られたデータを用いて結論を導く。すなわち、「実際にどうであるか」を知ろうとするのが科学なのである。
一方、哲学はむしろ、データのとれない領域に関して考える学問である。客観的な説明のつかない領域について自由に思索する学問であるために、その思索の材料も自由に選べるのだ。懐の広い学問だということもできよう。
▼宗教と哲学
人間の文化に密接にかかわっているものとして、宗教と哲学との関係も複雑だ。
神の存在について考えるという点で、この両者を厳密に区別することは難しい。人知を越えた存在について思いを馳せることは、それだけで哲学的な態度なのである。
また、信仰はそれ自体が、「よりよく生きる」ためになされるものであることも重要だろう。信仰を突き詰めると、それは必ずや哲学的思索に辿り着くはずだ。
たとえば、決定論(=「あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事のみによって決定している」とする立場)の考えかたは、宗教的な背景があってこそ成立するものである。実際に、決定論について論じられるとき、多くの哲学者はキリスト教の教義を引用している。
また、古代インド哲学では、そもそも哲学と宗教とを区別しようという発想すらなかった。宗教家たちは、哲学的な議論を重ねることで、より宗教への理解を深めていったのである。
このことからも、哲学と宗教は類似性が高く、不可分の概念であるといえる。
哲学の分類法
その対象が広汎であるがゆえ、哲学は分類法も多岐にわたる。以下に一例を示す。
▼学派からの分類
古代ギリシア哲学、自然主義、形而上学、イギリス経験論、ドイツ観念論、超越論的哲学、現象学、唯名論、大陸合理主義、実存主義、構造主義、プラグマティズム、新カント派、などなど……
▼立場からの分類
存在論、実在論、観念論、決定論、宿命論、機械論、二元論、一元論、懐疑主義、独我論、相対主義、などなど……
▼地域からの分類
大陸哲学、アメリカ哲学、インド哲学、日本哲学、西洋哲学、東洋哲学などなど……
▼主題による分類
科学哲学、論理学の哲学、言語哲学、倫理学、分析哲学、数学の哲学、法哲学、心身問題の哲学、政治哲学、戦争哲学、歴史哲学、生命倫理学などなど……
これら各分野についてそれぞれ細かく解説を加えるには、スペースも足りないし、また、記事が乱雑になってしまうおそれが高い。繰り返し述べているとおり、哲学はその領域があまりに広すぎるのである。ひとつの記事内ですべてを系統立てて解説することは不可能なのだ。
よって、関心のある分野については各自学習することが望ましいだろう。
「哲学」と「思想」の違い
哲学と類似した言葉に、「思想」がある。この二つはしばしば混同される。哲学者が思想家と呼ばれたり、その逆も然りであることがよい例だろう。
たしかに、知について論じるという点で、この両者には共通項がある。日常のなかではさほど区別する必要性はないように思える。
しかしながら、「哲学史」と「思想史」は厳密に異なっている。ここに、両者を区別するヒントがある。哲学史では哲学者しかあつかわないが、思想史では政治家や経営者といった、社会に大きな影響を与えた人物も含まれるのだ。
哲学者の永井均は、この区別を以下のように定義している。
「哲学は学問として『よい思考』をもたらす方法を考えるのに対し、思想はさまざまな物事が『かくあれかし』とする主張である」
哲学の現状
哲学はきわめて抽象的な概念をあつかう学問である。これは、言い換えれば、実生活の役に立たない非生産的な学問だということでもある。
学問の本義を考えれば、知的欲求を満たそうという哲学のこうした性格は、最も学問らしいものだといえるかもしれない。
しかしながら、現実の研究機関である大学では、研究費の予算がかぎられている。このため、大学の現場では哲学研究は非常に弱い立場に立たされている。
また、哲学における論争は、科学によって解決されないかぎり永遠に決着することはない。抽象的な議論が、結論も出ないまま延々と続くことに貴重な研究費を割くことへの批判もある。
大学が、企業に就職するためのプロセスとしての性格を強めている現在、哲学をとりまく状況はますます厳しくなっているといえる。
だが、そうした状況だからこそ、ますます真の哲学的態度が求められるのである。いかなる批判があろうと、些細な疑問をうやむやにせず真理に近づこうとすることが哲学だ。
今あえて哲学を学ぼうとする者は、それだけで哲学的な態度だといえるのかもしれない。
哲学-解説②
哲学とは、ギリシャ語原語のphilosophiaから見れば、「philos(愛)+sophia(知恵、知、智)」で、「知恵・叡智を愛する、希求する」という行為になる。
一般的には、「物事の根本原理をきわめる学問」とされる。
じつは、この「哲学とは何か?」自体がひとつの哲学的な命題となっており、多くの意見が出されている。
間違いのないところで言うなら「世界観の創出活動」であろう。
宗教との違いも、この世界観で考えればわかりやすくなる。
宗教というのは、創始者・開祖などと呼ばれる人々が作った「ある世界観を信仰する行為」である。
一方の哲学は、すでにある世界観ではなく、「自分なりの世界観を創出する行為・知的活動」である。
哲学においてももちろん、すでに誰か他の哲学者によって構築された世界観を勉強したり、同意・賛同したり、という活動は行われるが、哲学における究極的な目標は、自分なりの世界観を構築することにあると言えるだろう。
特に「自分の存在意義」、「生きることの目的」、「人生とは」といった命題は、誰もが少なからず心に思い浮かべるものである。
こうした命題に対し、自分なりの回答を提示し、ある種の世界観を示していくことが哲学なのである。
哲学書をちょっと紐解いてみると、やたら難解な言葉が羅列されている、と感じた人は多いであろう。
これは2つの理由が考えられる。
ひとつは、かつて古代ギリシャなどにおいて、哲学が科学をも含むあらゆる学問分野の基盤となっていたため、客観的な表現が多くなるためである。
もうひとつには、哲学は人間の思考やイメージを言葉で表現しようとするため、想起者によっては、とても複雑な表現や抽象的な表現を強いられてしまうことになるからであろう。
哲学において扱われる主な主題には、以下のようなものがある。
真理、本質、同一性、普遍性、数学的命題、論理、言語、知識、観念、行為、経験、世界、空間、時間、歴史、現象、人間一般、理性、存在、自由、因果性、世界の起源のような根源的な原因、正義、善、美、意識、精神、自我、他我、神、霊魂等である。
哲学の祖師、ソクラテス
古代ギリシャで生まれた哲学が現代まで連綿とその流れを継承しているのは、ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった、現代科学から見ても優れた思考・論理体系を古代において示した哲人たちの存在があったからである。
各哲人の詳細については別所に委ねるとして、ここではソクラテスに関するエッセンスのみを筆者なりの視点から記しておく。
●ソクラテス(BC469年頃 - BC399年4月27日)
「神のみぞ知る」という言葉、「倫理学」(人はいかに生きるべきかを探求する)、カウンセリングの素地である「問答法」等の生みの親である。
「はかない人間ごときが世界の根源・究極性を知ることなどなく、神々のみがそれを知る」という考え方がソクラテスの底辺にはある。
では、だから真理の探究はしなくても良い、ということではなく、「人間の探求心においては謙虚さが大切」ということを訴求しているのである。
●「無知の知」
ソクラテスはデルフォイのアポロン神殿において巫女から、「ソクラテスに勝る賢者はいない」という神託を受けた。
「そんなはずはない」と思ったソクラテスは、多くの賢者と言われる人物と対話をする。その結果、ほとんどの賢者は、「真・善・美・徳」について、「何も知らないのに知ったつもりでいる(=知らないということを知らない)」と指摘。
一方、ソクラテス自身は、「まだ知らないということを知っている」とし、これを「無知の知」と表現した。
「無知の知」がある分、自分に勝る賢者はいないと、ソクラテスは神託の正しさを確信したようである。
●問答法
またソクラテスは、弟子たちとだけでなく、街へ出かけて市井の人々とも「問答」によって対話をすることで、自身の哲学を広めることに生涯を費やした。
そのため自身の著作物は一切ない。
「問答」とは、一方的に自分の意見を相手に押し付けるのではなく、相手の意見をしっかりと聞いた上でその矛盾点を指摘したり、相互の誤解や不理解を正し、共有できる結論を導いていくことである。
こうしたソクラテスの問答法は、現代におけるカウンセリング法のベースにもなっている。
●ソクラテスの「魂」
ソクラテスは「魂」を高めることを重視した。
この魂とは、肉体とは不可分のものであり、「命」でもあった。
人は「己を知り」、「真・善・美」について探求し、「徳を積む」ことでその「魂」は高められると考え、人間の生き方において重要なものとした。
しかしこうしたソクラテスの考えは、政治家たちにとっては受け入れがたいものだったようだ。
ソクラテスが70歳になろうとする頃(B.C.399)、「ギリシア古来の神々を冒涜(ぼうとく)し、自らの神を作り出した。そして、若者たちを誤った方向に導いた」という罪状で裁判にかけられる。
●ソクラテスの弁明
その裁判においても、ソクラテスは臆することなく自説を述べた。
それが「ソクラテスの弁明」である。
「ソクラテスの弁明」
「世にもすぐれた人よ、君は、アテナイという、知力においても武力においても最も評判の高い偉大な国家の人でありながら、ただ金銭をできるだけ多く自分のものにしたいということばかりに気を使っていて、恥ずかしくはないのか。
評判や地位のことは気にしても思慮や真実のことは気にかけず、魂(いのち)をできるだけすぐれたものにするということに気も使わず心配もしていないとは。」
(田中美知太郎編 世界の名著6 プラトンⅠ中央公論社 ソクラテスの弁明より抜粋)
おそらくこのソクラテスの言葉は、あまりに神聖であり、堕落した政治家の心には、ナイフのような武器にでも感じられたのだろう。
この言葉の真意が政治家に届くことは無く、ソクラテスは「死刑」を宣告される。
ソクラテスは「他人を律するより先に、まず自らを正せ」という言葉を残し、潔く毒杯をあおってその生涯を閉じた。
スピリチュアリズムの祖師プラトンとイデア
●プラトン(BC427年 - BC347年)
ソクラテスの弟子だったプラトンは、哲学における巨星の1人であると同時に、スピリチュアリズムの祖師とも言えるだろう。
プラトンは、この世の目に見える世界は虚像であり、目に見えない世界である「イデア」こそが実像・実相であるとした。
●プラトンの「魂」
若き日のプラトンは政治家を志したこともあった。
しかし、師であるソクラテスの死刑はプラトンにとって、「政治家への絶望」だった。
そしてこれを機に、プラトンはソクラテスが重視した「魂」の存在をより掘り下げていくのである。
もしソクラテスの死刑が無かったら、神秘主義者プラトンはいなかったのかもしれない。魂の存在を掘り下げた結果、プラトンは「魂は永遠であり、輪廻転生を繰り返す」と考えた。
これはご存知のように、現代のスピリチュアリズムの大前提となっている概念である。
以下がプラトンの考えた「魂」である。
「プラトンの魂」
我々の魂は、かつて天上の世界にいてイデアだけを見て暮らしていたのだが、その汚れのために地上の世界に追放され、肉体(ソーマ)という牢獄(セーマ)に押し込められてしまった。
そして、この地上へ降りる途中で、忘却(レテ)の河を渡ったため、以前は見ていたイデアをほとんど忘れてしまった。
だが、この世界でイデアの模像である個物を見ると、その忘れてしまっていたイデアをおぼろげながらに思い出す。このように我々が眼を外界ではなく魂の内面へと向けなおし、かつて見ていたイデアを想起するとき、我々はものごとをその原型に即して、真に認識することになる。
●プラトンとイデア
人間においての真の実体は、「見えざる魂」としたプラトンは、あらゆる物事の背景には「見えざる世界」が隠されていると考え、これらを「イデア界」と呼んだ。
この「イデア」を現代のスピリチュアル用語で説明するならば、魂を含むすべての霊的エネルギー、気やプラーナなどと呼ばれる生命や宇宙に蔓延するエネルギー、人間においては運命や宿命など呼ばれるすべての事象を方向付けるエネルギーなどの総称、と考えていいだろう。
プラトンは「哲学」philosophia(=愛知)とは、「死の練習」であるとした。
そして真の哲学者とは、「真のphilosopher(愛知者)は、できるかぎりその魂を身体から分離開放し、魂が純粋に魂自体においてあるように努力する者」と定義したのである。
